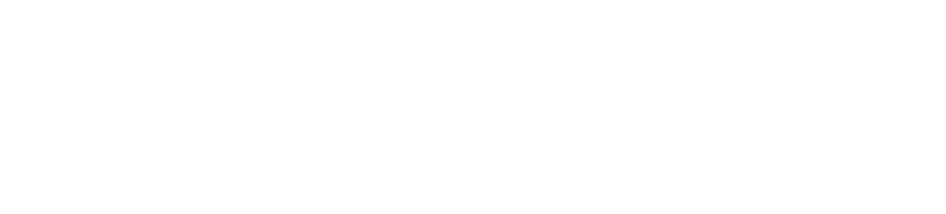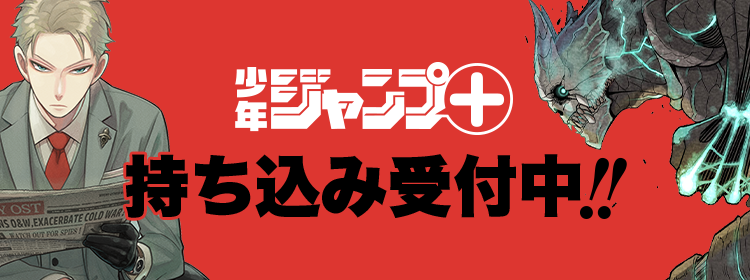いつも編集部ブログをお読みいただき、ありがとうございます!
少年ジャンプ+編集部のT橋です。
さて、皆さんは「オーディション番組」はご覧になるでしょうか?
「なぜ『ジャンプルーキー!』の編集部ブログでオーディション番組の話を…」と思われるかもしれませんが、
「見ず知らずの状態から出演者を応援してもらう」というオーディション番組の見せ方は、
「見ず知らずの状態からキャラクターを好きになってもらう」という漫画の見せ方にも通ずるところがある…と私は思っています。
今回は昨年から今年にかけて大きな話題を呼んだオーディション番組『timelesz project -AUDITION-』を参考に、「『読者に好きになってもらう』ためのキャラの作り方」について考察していきたいと思います。特にキャラ作りに難しさを感じている新人作家さんの参考になれば幸いです!
(なお本記事は、『timelesz project -AUDITION-』の番組終盤の展開についても一部言及しています。完全なネタバレを避けたい方は、番組をご覧になってから本記事をお読みいただくことを推奨いたします。)
www.netflix.com
※『timelesz project -AUDITION-』(以下、略して『タイプロ』)
STARTO ENTERTAINMENT所属の男性アイドルグループtimelesz(旧名:Sexy Zone)の、追加メンバー決定オーディションの様子を描く番組。
Netflixにて配信中。オーディションへの応募総数は18,922件。
結成12年超えの人気グループとしては異例となるオーディション企画は、国内で大きな話題を呼んだ。
NOSUKEさんは数々の人気アーティストのライブに出演経験のあるダンサーで、
timelesz/Sexy Zoneの多くの楽曲の振り付けを担当するなど、timeleszとの関わりの強い振付師でもあります。
『タイプロ』内でも、候補生に対して「僕が一番 より厳しい目で見るつもりでいます」「もう入れさせない目で見てます」と、
長くtimeleszと関わり、グループへの強い愛情があるからこその厳しい思いを語ったNOSUKEさん。
番組内でも、厳しい言葉で候補生たちを叱咤激励するシーンが目立っていました。
そんな中話題になったのが、五次審査終了後の NOSUKEさんの涙でした。
五次審査の通過者と非通過者が発表された後、timeleszメンバーや候補生たちからは見られない場所で、NOSUKEさんは声を押し殺しながら激しく涙を流します。
長い審査を経て、厳しい課題を乗り越えてきたtimelesz候補生たちへの想いが溢れたであろう瞬間は、大きな驚きと話題を呼びました。
このシーンについては、
・候補生に対して厳しい態度を取ることの多かったトレーナーが
・審査結果の発表後に激しく泣いている
ので、そうではない人が泣いているのと比べて意外性が生まれたのかと思います。
このように「その人が持つイメージと真逆の行動をさせる」ことは、その理由がしっかり読者に共有されれば、漫画のキャラクターにおいても魅力的な「ギャップ」に繋がることは多々あります。
『タイプロ』内ではその他にも強い「ギャップ」を持つ出演者が数多く登場しますので、
「その人のどのようなギャップが魅力につながっているか」を考えて言語化すると、漫画のキャラクターにも活きるかもしれません。
『タイプロ』への参加発表前は5.5万人ほどだった寺西さんのInstagramのフォロワーは、現在は130万人を突破しました。
寺西さんは2008年、事務所に入所。timeleszメンバーの菊池風磨さんとは同期入所でした。
バックダンサーの仕事を中心にキャリアを積んだ後、『タイプロ』までグループに所属することはなく、俳優としての仕事をメインに活躍されていました。
一方で菊池さんを初めとする同年代がグループでアイドルとして活躍していく中、
「芝居をやりたいという気持ちも嘘ではないが、やはり歌って踊るアイドルへの想いも捨てきれない」と今回のオーディションに参加。
オーディション中はバックダンサーや俳優の経験で培った圧倒的なスキルで他の候補生をリードし、
芸歴十数年の経験値からくるアドバイスで悩める10代の候補生を導いたり…とそのスキルのみならずリーダーシップも高く評価されていました。
このように
共感できるポイント:同期が活躍していく中、かつての夢に未練を感じている
憧れられるポイント:とはいえ目の前の仕事には全力で向き合ってきたので、スキルも自信もしっかり身についている
と「共感」「憧れ」どちらもしっかり立っているのが寺西さんの魅力の一つだと感じています。
このような「共感」「憧れ」を軸としたキャラの立て方は漫画内でもよく見られるものです。
『タイプロ』をはじめとしたオーディション番組で、
好きな出演者の「共感できるポイントはあるか」「憧れられるポイントはあるか」を探してみるのも、良い思考実験になるかと思います。
漫画のキャラクターにも活かせそうな好感度の上がるポイントが少なからずあることが少しでも伝わったのではないか、と思います。
キャラ作りで迷ったら、自分の好きな実在の人物の「どこが好きなのか」を突き詰めて考えるのもいいかもしれません!
■現在募集中!
『少年ジャンプ+漫画賞 2025年5-6月期』はコチラ↓
『ジャンプ+連載争奪ランキング』はコチラ↓
『少年ジャンプ+』への持ち込みはコチラ↓